
はじめまして。このブログを運営している、non(ノン)です!
突然ですが、あなたはこれまでに、こんな風に感じたことはありませんか?
- 一日、誰かと一緒に過ごした日は、家に帰るとぐったり疲れ切ってしまう…
- 相手の機嫌や場の雰囲気を察知しすぎて、言いたいことが言えなくなってしまう…
- 他の人は気にしないような、小さな物音や光、匂いが気になって仕方ない…
もし、少しでも「私のことかも」と感じてくれたなら、何かのお役に立てるかもしれません!
あなたが感じてきた、その何らかの「違和感」の正体は、もしかしたら「HSP」という、生まれ持った”あなたの個性”が理由である可能性があります。
この記事では、「HSPとは、そもそも何?」という基本的な知識から、実はいくつか存在するHSPのタイプまで、私の実体験を交えながら分かりやすく解説します。
この記事を読み終わる頃には、あなたがずっと抱えてきた「なぜだろう?」という疑問が少しでも解消されると嬉しいです。
そもそもHSPとは?
まずHSPとは、病気や何かの障害ではありません。
心理学者のエレイン・アーロン博士によって提唱された心理学的な概念で、「生まれつき、刺激に対して非常に敏感な気質を持った人(Highly Sensitive Person)」のことを指す言葉です。
人口の約5人に1人がHSPにあたると言われています。
これって、学校の1クラスが40人だとしたら、その中に8人くらいはいる計算になります。 どうでしょう?「思っていたより、ずっと多いかも」と感じませんか?
同じように感じている人が、あなたのすぐそばにもいる。そう思うと、少し心強くありませんか?
次にHSPには、その頭文字をとった「DOES(ダズ)」と呼ばれる、4つの基本的な特徴があります。この4つ全てに当てはまるのが、HSPの定義とされています。
D:深く考えをめぐらせる (Depth of processing)
物事を処理するとき、深くじっくりと考えるのがHSPの基本スタイルです。表面的な情報だけでなく、その裏にある背景や、未来に起こりうる可能性まで、無意識のうちに考えを巡らせます。
【良い面】
慎重に行動できるため、他の人が見逃すようなリスクに気づけたり、物事の本質を捉えるのが得意です。
【人より大変な面】
例えば、何かを決断するのに時間がかかったり、考えすぎてしまって、なかなか行動に移せないことがあります。
O:刺激を受けやすい (Overstimulation)
心のアンテナの感度が高く、外部からの刺激を人一倍強く受け取ってしまいます。HSPにとっての世界は、まるで「音量も明るさも、常に少し大きめに設定されているテレビ」を見ているようなものかもしれません。
【良い面】
他の人が気づかないような小さな変化や、美しいものに感動できる、豊かな感受性を持っています。
【人より大変な面】
例えば、人混みや騒がしい場所に行くと、情報量が多すぎてぐったり疲れてしまったり、一日の終わりに一人で心を鎮める時間が必要不可欠だったりします。
E:共感力が高く、感情反応が強い (Emotional reactivity / Empathy)
人の気持ちを、まるでスポンジのように吸収してしまう能力です。相手の感情が、言葉にしなくても自然と伝わってきて、自分のことのように感じてしまいます。
【良い面】
相手の気持ちに深く寄り添えるため、人から相談されたり、信頼されたりすることが多いです。思いやりが深い、最高の聞き役になれます。
【人より大変な面】
例えば、悲しいニュースを見ると何日も落ち込んでしまったり、相手の機嫌に振り回されて、精神的に疲れてしまうことがあります。
S:些細な刺激を察知する (Sensitivity to subtleties)
五感が鋭く、他の人が気づかないような、本当に些細な違いを察知します。これは、高性能なセンサーが常に作動しているような状態です。
【良い面】
芸術や音楽を深く味わえたり、相手の表情や声色のわずかな変化から、その人の本心を見抜くのが得意だったりします。
【人より大変な面】
例えば、服のタグがチクチクして集中できなかったり、かすかな匂いが気になって気分が悪くなったりすることがあります。

DOESの4つの特徴、改めて「私のことだ…」と思いながら解説を書いていました。
周りに気を遣いすぎて、意見を求められても言葉に詰まってしまう(D)
人が多い場所に行くと何もしていなくてもストレスを感じる(O)
悲しいニュースを見ると身内のことのように号泣したり(E)
他の人が気づかないような匂いや味の違いが分かったり(S)
そういう性格の人間なんだなと思っていましたが、この「HSP」という言葉に出会って、点と点が繋がったような気がしました。
また、「HSP」と一言で言っても、実は全員が同じではありません。
刺激に対する好みや、人との関わり方によって、大きく4つのタイプに分けられるんです。
※これから紹介する4つのタイプ分けは、HSPについての自己理解を助けるために広く使われている考え方ですが、
医学的な診断基準ではありません。あくまで「自分の個性を知るヒント」として、参考にしてみてくださいね。
では、それぞれのタイプを、見ていきましょう!
① HSP(内向型HSP)|静けさを愛する、王道の繊細さん
HSPのうち約7割がこの内向型だと言われており、いわゆる「繊細さん」のイメージに最も近いのがこのタイプです。
外部からの刺激をなるべく避け、ひとりで過ごす時間や、静かで落ち着いた環境を好みます。
感受性が豊かで、自分の内面とじっくり向き合うことで、エネルギーを充電します。
【他のタイプとの比較】
後述するHSS型HSPのように自ら刺激を求めることは少なく、人と一緒にいることでエネルギーを得ることもありません。自分の「安全基地」となる場所で過ごすことが、心の安定に繋がります。
例えば、休日は家で本を読んだり、好きな映画を観たりして過ごすのが、何よりの幸せだと感じるタイプです。
② HSS型HSP(刺激追求型HSP)|好奇心と繊細さの板挟みタイプ
「ブレーキとアクセルを同時に踏んでいる」と表現される、少し複雑なタイプです。
好奇心が旺盛で、新しいことや未知の体験に強く惹かれますが(HSS:High Sensation Seeking)、根っこはHSPのため、いざ挑戦してみると刺激が強すぎて圧倒され、すぐに疲弊してしまいます。
【他のタイプとの比較】
一般的なHSPが刺激を避けようとするのに対し、HSS型HSPは自ら刺激に飛び込んでいきます。
しかし、刺激に対する耐性がないため、そのギャップに苦しみ、「自分は一体何なんだろう?」と悩む人が多いのが特徴です。
例えば、海外旅行の計画を立てるのは大好きだけど、いざ現地に着くと人の多さや文化の違いに圧倒されて、ホテルでぐったりしてしまうようなタイプです。
③ HSE(外向型HSP)|実は繊細な、社交的タイプ
HSPのうち約3割を占める、人と関わることが好きな「外向的な繊細さん」です。
初対面の人とも臆せず話せたり、グループの中心になれたりするため、周りからはHSPだと気づかれにくいかもしれません。
しかし、気質はHSPなので、人と会って楽しんだ後は、ひとりの時間でしっかりと心を回復させる必要があります。
【他のタイプとの比較】
HSP(内向型)との一番の違いは、人との交流を(ある程度は)エネルギー源とするところです。
しかし、HSPではない一般的な外向型の人と違い、刺激に対する許容量は少ないため、「楽しかったけど、ものすごく疲れた…」という経験をしやすいのが特徴です。
例えば、飲み会では盛り上げ役になるけれど、二次会には行かずにそっと一人で帰りたくなるようなタイプです。
④ HSS型HSE(刺激追求・外向型HSP)|最もアクティブな、繊細リーダータイプ
人と関わることも、新しい刺激も大好きな、最も活動的なタイプです。
リーダーシップを発揮したり、新しいプロジェクトを立ち上げたりと、エネルギッシュに行動します。HSPの中では最も少数派と言われています。
【他のタイプとの比較】
4タイプの中で最も外向的で刺激を求めますが、HSS型HSPと同様に、刺激に圧倒されやすい繊細さを内に秘めています。
自分のキャパシティを正確に把握し、意識的に休息をとることが、このタイプにとっては非常に重要になります。例えば、会社の新規事業のリーダーとして活躍する一方、週末はスマホの電源を切って、誰とも連絡を取らずに過ごす、といったバランスの取り方をします。

ちなみに、私は4タイプの中だと、好奇心旺盛で新しいもの好きなので
基本は「HSS型HSP(刺激追求型HSP)」ですが、
初対面の人と話すことが苦じゃないけど、精神疲労はしっかりするので少し「HSE(外向型HSP)」の気質も混ざっているのかな、と感じています。
タイプは、必ずしもどれか1つにきっちり分類されるわけではないので、「自分はこの要素が強いかな?」というくらいの気持ちで、自己理解のヒントにしてみてくださいね。
まとめ:自分の「トリセツ」を見つける、はじめの一歩
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
HSPの基本的な知識から、ご自身のタイプまで、何か新しい発見はありましたか?
あなたがこれまでに何らかの「違和感」を感じてきたのであれば、それはあなたがそれだけ多くのことに気づける、心豊かなアンテナを持っていることの裏返しです。
私はHSPという言葉を知ってから、「治す」や「克服する」といった考え方ではなく、
「自分の生まれ持った特徴を理解し、うまく付き合っていく」という姿勢が、とても大切だと感じました。
まずは、「私には、こういう個性があるんだな」とご自身のタイプを知ることが、あなただけの「トリセツ(取扱説明書)」を見つけるための、大切なはじめの一歩です。
このブログでは、その「トリセツ」を見つけるためのヒントを、私のリアルな同棲生活の経験談とともにお届けしてまいります。
一緒に、自分にとって一番心地よい生き方を、見つけていきましょう。
参考文献
- The Highly Sensitive Person(https://hsperson.com/)
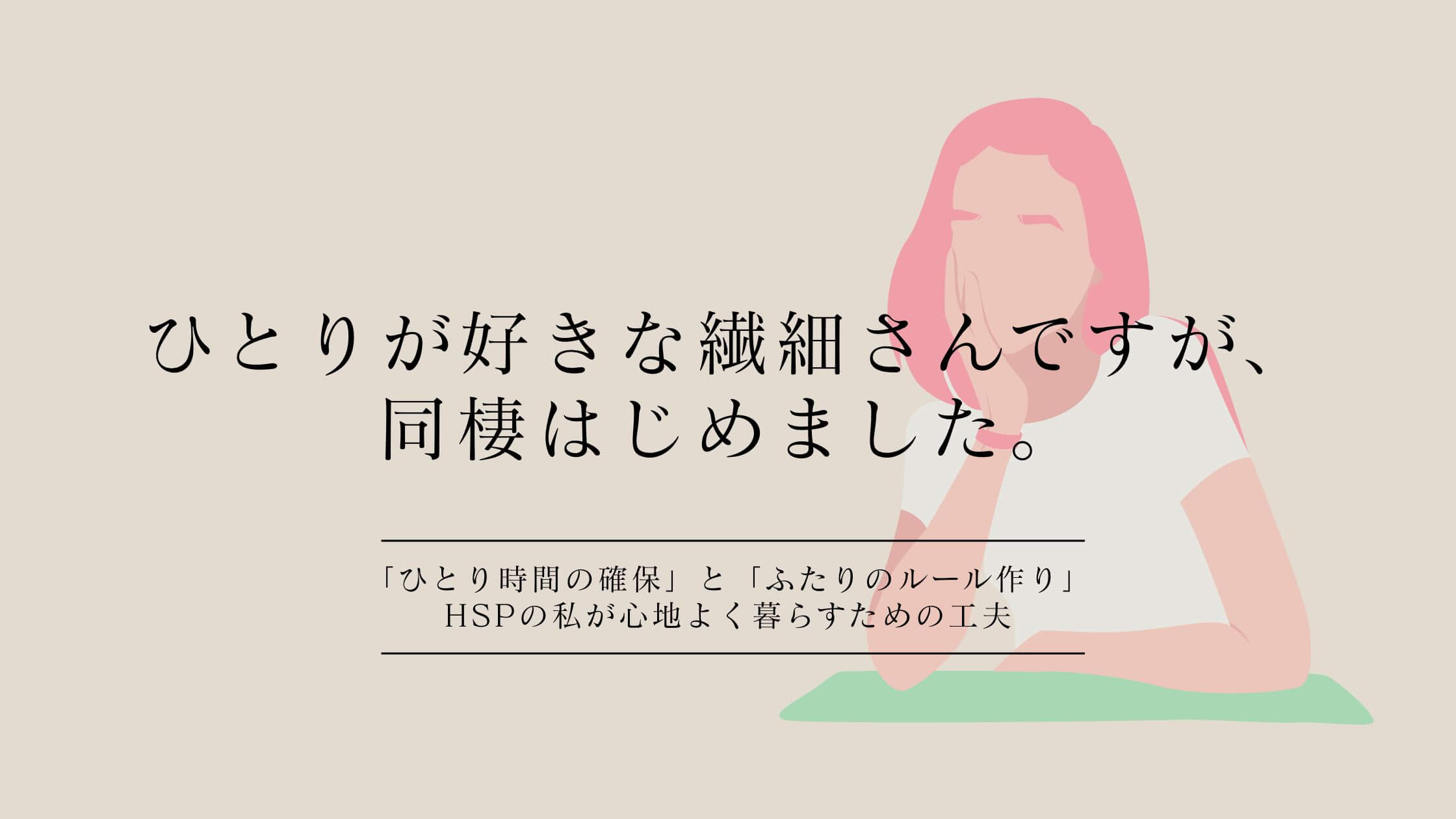
がフワフワと浮かんでいるが、その-1.jpg)

コメント